映画:『パリ20区、僕たちのクラス』は、移民の子弟の多い「パリ20区」(⇒ 小生、この「パリ20区」、全く存じ上げませんでした。)地区のある中学校で、理想主義に燃えた教師の奮闘と生徒とのやりとりを、ドキュメンタリーかと見まがうタッチで描いた作品です。
(1)映画について
第61回カンヌ国際映画祭で、審査委員長ショーン・ペンが絶賛しパルムドールに選んだ奇跡のような傑作、といわれています。21年ぶりに、フランス映画にパルムドールの栄誉をもたらしました。新聞や雑誌の映画評が、あまりにも高評価なので、小生も、久しぶりに“岩波ホール”へ足を向けました。
この映画が、多くの方々から評価を受けるのは主に、以下の3点です。
1. ドキュメンタリーとしか思えないほどの自然な演技に驚嘆し、先の読めないストーリー展開に胸を躍らせること。
2. フランソワ役の原作者フランソワ・ベゴドーをはじめ、映画に登場する教師も生徒もすべて素人なのに、ローラン・カンテ監督による丹念なワークショップの賜物か、別人になり切る見事な演技を見せてくれること。
3. 安直な和解とは無縁なリアリティに満ちた展開が、観る者を唸らせること。つまり、奮闘する教師・フランソワの思い描くように事態は展開しないのです。しかし、だからこそ、オーディエンスが、いつの間にか、作品に登場する生徒の誰かに、自らの中学生時代に自分が出会ってきた誰かを重ね合わせ、感情移入せずにはいられなくなるのです。
原題は『Entre les Murs』で、直訳すれば「壁の間で」となりますが、なぜか日本人のブログやWeb上での紹介では「壁の中で」と訳しているケースが多いそうです。原題は、教室内コミュニケーションにおける教師と生徒との間の障壁、そして生徒の中での民族間の障壁を象徴しているものだと思います。原作者本人が脚色に携わると同時に自ら教師役として出演しています。
(2)ストーリー
舞台は、移民が多く暮らすパリ20区の公立中学校・新学期の教室。この中学では生徒の大半が移民の子弟で、母語も出身国もバラバラ。そんな中で、正しい国語を身につけさせることこそ生徒たちの将来の幸福につながるという信念を持つ主人公のフランス語教師・フランソワが、様々な出身国を持つ24人の生徒たちが混じり合う教室のなかで、思いがけない反発や質問に翻弄されてしまいます。現実は情熱だけで解決できるような簡単なものではないのです。
例えば、去年は素直だったクンバは反抗的な態度で教科書の朗読さえ拒否する始末。また、自己紹介文を書かせる課題が大きな波紋を巻き起します。教室の中は真剣勝負の場です。教師も生徒も真っ向からぶつかり合います。ゆえに言葉というものの重要性が浮き彫りになります。誤解も批判も怒りも失望も、そして希望も言葉あってこそのもの。子どもたちのフランス語の力は、確かに日常会話ならほぼ不自由なく使えます。しかし動詞の活用は不確かだし、文語で主に使われる接続法の活用や、抽象的な単語は十分な理解が出来ない状況…。
さらに、フランス人の親は、この学校はレベルが低いから自分の息子は転校させたい、と言い出すような学校であります。始業のベルが鳴ってもお喋りはやまず、授業に身が入らない子どもも多いのです。教師の中でも、レベルの低い馬鹿どもを相手に小学校で教えるようなことから教えなきゃならないのは耐えられないと愚痴をこぼすような者がいる状況です。ちょっとすればすぐ注意力が逸れたり、教師の指示に従おうとしない生徒たちに手を焼く毎日です。生徒の反抗的な態度に、フランソワ自身、頭に来て椅子を蹴飛ばして憂さを晴らすことも・・・。
しかし、生徒たちが教師を恐れなくなり指示を聞かないからと、ポイント減点制を導入し、一定のポイントに達した生徒は教育委員会に退学を諮ることにしようという一部の教師の提案には、フランソワは断固反対する。また、親がフランス語を話せず、本人も自分の学業に自信を持てない生徒の長所を発見して、彼の才能を発揮できる機会を作り、学業を続けさせる意欲をかき立てることにも成功します。
(そのようななかで、決定的な事件が起こります。)
生徒の成績評価会議に、生徒代表としてオブザーバー参加していた二人の女子生徒が、無責任にもそこでの会議内容をクラス内で話し、成績の悪い生徒を馬鹿呼ばわりしたことに対し、フランソワは怒って、ついその生徒をpetasse(ずべ公、売春婦)と呼びつけてしまうことで、フランソワのクラスにおける信用は一夜にして瓦解してしまいます。彼の努力は一部功を奏しながらも、結局はほんの一瞬の失敗により全ての努力は水の泡となり、生徒たちとフランソワの間の信頼関係は崩壊するのです。さらに手を掛けた生徒から退学者も出てしまう。さて、フランソワは、生徒達との信頼関係を取り戻せるのか・・・。
(3)監督について
監督のローラン・カンテは1961年フランス、ドゥー=セーヴル県、メル生まれです。1999年『人材 (Ressources humaines)』で労使対立に起因する労働者の苦難を描いて国際的に注目されます。さらに2001年リストラされたものの家族に悟られないよう仕事に行くふりをする男を描いた『時間労働 (L'imploi du temps)』、2005年、1970年代末を背景に、ハイチへ黒人男を漁りに行く3人のフランス人白人中年女性を描いた『南へ (Vers Le Sud)』を撮っています。
今回のこの作品で、カンテ監督が子供たちから自然な演技を引き出した秘密は、撮影前のワークショップにある、と言われています。中学校で希望者を募って週1回、約7ヶ月間、彼ら一人一人の個性を把握し、能力を探り続けた、そうです。そして、最後まで通い続けた生徒たちの中から、この24人を選んだそうです。子供たちの設定は、すべてフィクションです。彼ら自身の性格を少し取り入れたキャラクターもあるが、ほとんどが自分とは全く違う生徒を演じています。監督を始めスタッフ、キャストの大人たちは、彼らの潜在能力に感動した、とコメントしています。
(4)小生の感慨
教師たちは、決して聖職者ではなく、悩み苦しむ人間らしい労働者として描かれます。
小生、様々な出会いを求めて日々活動しておりますが、今、小生が語り合いたい方、それは「希望を求めて、悩み苦しみ、日々試行錯誤しておられる方」です。主人公が、真面目であるが故に、生徒の不真面目さが許せず生徒とぶつかり合う姿には、「俺、あんたの気持、よく判るよ!」と声を掛けたくなります。
試行錯誤を行う人間は「不器用」という言葉で、片付けられてしまう昨今ですが、試行錯誤を避けていては「希望」を勝ち得ることは不可能だと思います。私達は、無人島で暮らすロビンソー・クルーソーではないのですから・・・。
自分のセンスを全く理解しようとしない方とのコミュニケーションは非常に不愉快なものです。しかし、この不愉快さを、いかに克服していくのか、に悩むのです。この映画の主人公も、反抗的で、自己中心的で、ヒトの気持(=紳士に生徒を心配する気持)を理解しようとしない生徒と対峙することは非常に苦痛であった筈です。しかし、彼は試行錯誤を続けた。小生、ここに彼と共感するのです。全てが生々しく、あたかもドキュメンタリーの様にこの先どう転ぶか分からない緊迫感に溢れている「リアリティ」を突きつける作品です。
それにしても、成績判定会議に生徒代表がオブザーバーとして立ち合うなど、彼我の学校文化の差には驚かされます。また生徒たちも、騒いだりするとは言え、基本的には先生に注目して欲しいし、先生とコミュニケーションを取ろうとする姿勢が、一般的な日本人あるいは日本の学校システムとかなり違うように思われます。
まぁ~、ここで日仏間の学校教育のありかたを論ずるつもりはありません。小生、スクリーンのなかで、本気で悩んでいる教師・フランソワと出会い、「悩むこと、それは素晴らしいこと」と言う思いを強くしました。そうした気持を、今回はお伝えしたかったのです。
さぁ~、本日の「酒の肴」、御堪能頂けましたでしょうか。それでは、また・・・。
skip to main |
skip to sidebar

酒の肴の文学と映画の話

- 及川 譲
- おいかわ ゆずる。 1963年東京生まれ。千葉大学法経学部卒業。 専門は文学評論・映画評論。 鑑賞した全ての作品からリスペクトする部分を見出し、ヒューマニズム溢れる論評を展開するその独特な筆には定評がある。 酒と文学と映画を愛する、人間の内面に切り込んでいく評論家。
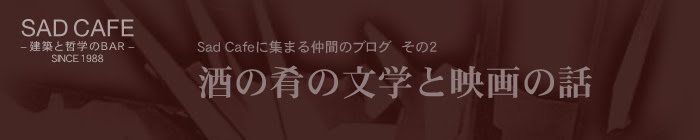
0 件のコメント:
コメントを投稿