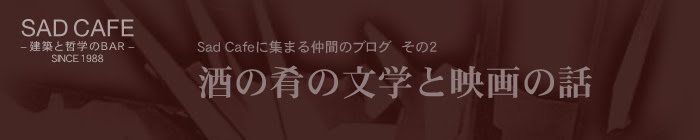スパイ映画・『007』も好いけれど、実話をもとに製作された「スパイ映画」は、アクションシーンこそありませんが、フィクションの世界とは異なる面白さを我々に提供してくれるものです。さて、「スパイ映画」を素材にした「酒の肴」・二品目です。
先ごろ、アメリカでロシアのスパイが大量摘発され、ロシアが押さえていた旧西側スパイと交換されるという事件が起きました。まるで古いサスペンス映画を倉庫から引っ張り出して見せられているようで、まあ驚きで文字通り世界の注目を集めました。摘発されたスパイたちが、いかなる「情念」のもとに、どんな「獲物」と「成果」を上げていたのか、まだよくわからないそうです。ただ、市民生活にとけ込んだ暮らしぶりや経歴を見ると、ヒットエンドランのような短期の工作員ではないのでありましょう。
昨今は、今回紹介する「フェアウェル」の時代のような、世界大戦につながりかねないような緊迫感はありませんが、家庭人を装いながら(いや、実際に家庭人だったのでしょう。)、任務に忠実であろうとした「21世紀のロシアのスパイたち」の心の風景は、どんなものだったのでしょうか。美人がいたからというわけではなく、これは将来必ず味のある映画になると小生は思うのです。特に、これから紹介する映画『フェアウェル さらば、哀しみのスパイ』を鑑賞した後には・・・。
「真実」であるが故に、迫り来るものを感じます。「真実」であるが故に、主人公となるスパイたちの人間味に酔いしれ、彼らに哀愁を感じるのです。そして、「世界外交陰謀の恐ろしさ」も味わうことになります。
(映画『フェアウェル さらば、哀しみのスパイ』)
20世紀最大のスパイ事件のひとつと言われる「フェアウェル事件」、それは1980年代初頭ブレジネフ政権下のソ連で起りました。KGBのグリゴリエフ大佐(実名:ウラジミール・ヴェトロフ)が、自らが所属するKGBの諜報活動に関する極秘情報を、当時、東西冷戦時代の敵陣営であるフランスに受け渡したのです。しかもこの超大物スパイが提供した莫大な資料には、ソ連が長年調べ上げたアメリカの軍事機密や西側諸国に潜むソ連側のスパイリストなどが含まれ、まさに世界のパワー・バランスを一変させかねないほどの破壊力を秘めたトップシークレットでありました。だから、一般人は、この事件についてそれほど知りえないのです。グリゴリエフのコードネーム「フェアウェル(いざ、さらば)」を冠して「フェアウェル事件」と呼ばれるこの史上空前のスパイ事件は、実際に当時のソ連を震撼させ、アフガニスタン侵攻の失敗とともに、のちの共産主義体制崩壊の大きな切っ掛けになりました。
なぜ、スパイ・「フェアウェル」は祖国を裏切るという死と背中合わせのリスクを冒したのでしょう。「世界を変えてみせる。祖国・ソ連のために、そして現在の自分を“国家の犬”と批判する次世代を生きる息子のために・・・」という思いが、彼を駆り立てたのです。
事実は小説よりも奇なりであります。今回紹介する作品・フランス映画『フェアウェル/さらば、哀しみのスパイ』は、そんな時、東西冷戦構造崩壊につながったともいわれる、実際の大型スパイ事件をドラマにした作品です。ジェームズ・ボンドのような秘密工作員が大活躍する? ノーであります。祖国と家族を愛し、よれよれに疲れ、しかし、一筋の希望を捨てなかった中年男・KGBのグリゴリエフ大佐(実名:ウラジミール・ヴェトロフ)が世界を動かしたのです。
舞台は1980年代初め、ブレジネフ体制末期のソ連。
すべてに行き詰まった祖国に絶望し、再生のためには体制を崩壊させ、新たな革命を経るしかない。こう決意したKGB(ソ連国家保安委員会)のグリゴリエフ大佐は、フランス人技師ピエールを通じ、機密情報を西へ流し始める。まず、西側のトップシークレットがソ連に漏れているという事実と証拠。そして、ついには西側で活動しているソ連のスパイたちの所在も知らせます。
米国のホワイトハウスやCIAのトップは、ソ連への情報漏えいの実態を知ってがく然とする一方、大佐の情報でスパイを大量摘発し、ソ連の海外諜報(ちょうほう)活動網を壊滅状況に追い込みます。しかし、国家や国際パワーゲームの当事者である為政者たちには、自分たちが利用するスパイの個人的な思いなどどうでもよく、まして彼らの友情や家族愛など想像さえしなかったでありましょう。しかし、この作品は彼らの友情や家族愛などを見事に描いたのであります。
初めは素っ気なかったが、次第に友情を深めるグリゴリエフ大佐とピエールが、この映画の主人公です。この大佐は実名ウラジミール・ヴェトロフ、事件当初53歳でした。スパイ史であるJ・T・リチェルソン著「トップシークレット」(太陽出版)によると、ヴェトロフはKGBで科学技術のスパイを担当する第1総局のT局幹部となっております。60年代にフランスのパリに駐在した経歴があり、その時知り合った実業家を通じ、手紙でフランスの防諜機関DSTに接触、情報提供を申し出ます。DSTはヴェトロフに英語で「フェアウェル(いざ、さらば)」という暗号名を与えます。
グリゴリエフ大佐から提供される情報によって、科学や技術に関しソ連が西側から収集していた膨大な情報が分かり、設計書や解析がおびただしく開示されていきます。西側で活動する「ラインX」という大量のKGB要員のリストも明らかになります。勝負あった、である。
「フェアウェル」の活動は長くは続きませんでしたが、その効果は決定的だったのです。もちろん、グリゴリエフ大佐彼の命運は波乱万丈です。詳細は、どうぞ劇場で・・・。
映画では、グリゴリエフ(ヴェトロフ)大佐と、情報受け取り役のピエールの次第に深まる友情と、双方の家庭内の亀裂、愛憎があざなえる縄のように描かれます。
大佐は1955年に大学を出た、理工系であります。そのころ、ソ連は宇宙ロケット開発競争で米国をリードし、スプートニクの打ち上げ成功が世界を驚かせました。有人衛星もソ連が初めて成功させました。そのころを誇らしげに大佐が回想するシーンがあります。印象深いシーンです。ソ連にも栄光の時があったのです。 だが、80年代。その栄光は薄れ、情報を盗むことでしか西側との科学競争についていけない国の実態に大佐は絶望します。
一人息子は遠い西側の自由にあこがれ、手に入れたロックバンド「クイーン」の音楽テープに夢中となります。この子の時代には新しい国に、と大佐はひそかに願います。発覚、破局の時がくる。大佐から情報を受け取っていたフランス技師・ピエールは妻子を車に乗せて雪の道を必死に疾走し、国外脱出を図ります。そして、仰天すべき事実を知ることになります。そこにはむき出しの国家のエゴ、裏にうごめくスパイの素顔があったのです。
「世界を変えてみせる。祖国・ソ連のために、そして現在の自分を“国家の犬”と批判する次世代を生きる息子のために・・・」という信念が、ひとりのスパイを創り上げたのです。しかし、「ソ連のため・・・」を世に問うには時期尚早でありました。なにしろ、ブレジネフ政権下です。真実を知るまでは、大佐の家族は、「大佐は国家の犬」、という認識さえ持っていました。「国家の犬」が「ソ連を変える」という信念を持ってスパイ行為をしていたのですから、事実は小説よりも奇なりであります。
スパイ映画でありますが、それはそれは上質なハードボイルド作品であります。どうぞ、グリゴリエフ(ヴェトロフ)大佐とピエールの友情に酔いしれて下さい。そして、先ごろ、アメリカで摘発された「ロシアのスパイ」、彼ら彼女らの思いを想像してみて下さい。上質なハードボイルドが創造できませんか・・・・。
ジェームズ・ボンドのような秘密工作員が大活躍する? ノーであります。
でも、「スパイ映画」、面白いですぞぉ~。
2010年8月23日月曜日
スパイ映画を語る。①映画『敵こそ、我が友』 ~戦犯クラウス・バルビーの3つの人生~
スパイ映画『007』も好いけれど、実話をもとに製作された「スパイ映画」は、アクションシーンこそありませんが、フィクションの世界とは異なる面白さを我々に提供してくれるものです。今回は、そうした実話に基づいて製作されたスパイ映画を2作品、2回に分けてご紹介しましょう。こうしたスパイ映画は「真実」であるが故に、迫り来るものを感じます。「真実」であるが故に、主人公となるスパイたちの人間味に酔いしれ、彼らに哀愁を感じるのです。そして、「世界外交陰謀の恐ろしさ」も味わうことになります。
(映画『敵こそ、我が友』 ~戦犯クラウス・バルビーの3つの人生~)
『クラウス・バルビー』という人物を知っていますか? 小生は、この人物の存在を、映画『敵こそ、我が友』を通して初めて知りました。彼は、1935年22歳でナチス・ドイツ親衛隊に所属してから、1987年フランスでの裁判で“終身刑(フランスは死刑がないので)”を宣告されるまでに、残虐で欺瞞に満ちた人生を送ります。本作品は、彼の人生を、「オーラル・バイオグラフィー」(いろんな人が彼について話すことで、その人物を浮かびあがらせる特殊な手法)の手法で描いた、ドキュメンタリー作品です。全編、彼に関わった人々のインタビュー(彼・本人のインタビューも含む)と、裁判映像で構成されています。
彼は、ドイツのノルトライン=ヴェストファーレン州で生まれ、1925年に、父親の転勤に伴いトリーアへと移動しました。1933年には、学生の身分ながら当時ドイツで勃興してきたナチス党のために働き、1935年には親衛隊情報部に入ります。 1939年9月に第2次世界大戦が勃発し、1942年にはドイツ占領下のオランダに赴任し、その後、フィリップ・ペタンが首班を務める親独政府であるヴィシー政権下のフランスのディジョン、リヨンに赴任します。1945年5月の終戦までの間に、ヴィシー政権下のリヨン市の治安責任者として対独抵抗運動を鎮圧する任務に就いており、8千人以上を強制移送により死に追いやり、4千人以上の殺害に関与し、1万5千人以上のレジスタンス運動の参加者に拷間を加えた責任者とされています。しかし実際には、この数字をはるかに上回る数のレジスタンスのメンバーやユダヤ人を虐殺した責任者と考えられており、また、孤児院に収容されていた44人の子供の虐殺に対する責任者とも言われたほか、レジスタンス指導者だったジャン・ムーランを逮捕し死に追いやったとのちに供述しています。フランス人は、彼に『リヨンの虐殺者』という異名を与えたそうです。
大戦後、本来ならばすぐにでもニュルンベルク裁判などの連合軍による裁判で裁かれてもおかしくなかったのですが、アメリカ軍は、フランス政府が戦犯として追求するバルビーを、当時ヨーロッパで始まりつつあった冷戦下における対ソ及びドイツ共産党員に対する情報網の設置に役立つ人物と判断し、1947年からアメリカ陸軍情報部隊(CIC)の工作員として利用します。
やがてフランスの諜報機関は、アメリカがバルビーをかくまっているという事実を嗅ぎつけ、アメリカにバルビーの引き渡しを要求しはじめました。しかしフランス政府の度重なるバルビー引き渡し要求にもかかわらず、バルビーの利用価値を高く評価していたアメリカは引き渡しを拒否し続けます。フランス政府により高まる引き渡し要求に、アメリカはバルビーを国外に逃すことを画策し、バルビーはCICが用意した「クラウス・アルトマン(Klaus Altmann)」名義のパスポートと必要書類一式を受けとり、1950年12月に家族と共に反共産主義のバチカンの庇護のもとに南アメリカに旅立ち、ファン・ペロン政権下のアルゼンチンを経て、1951年4月23日に家族と共にボリビアのラパスに到着します。フランスに彼の素性を察知されると、アメリカは『ラットライン』(ねずみの抜け道)と呼ばれた、逃走ルートを用意しました。しかも、この策動には、バチカン右派の神父たちが深く関わっていました。彼に限らず、バチカン右派の聖職者によって、ナチス残党の多くは海を渡ったようです。
1951年、彼は偽名『クラウス・アルトマン』を使い、ボリビアに潜入します。当時のボリビアは、冷戦下においてアメリカが支援する反共的な軍事政権の支配下にあり、戦前からのドイツ系移民の影響力も強かったこともあり、チリなど周辺国に住む元ナチス党員らと連絡を取り、同時に同国の軍事政権との関係を構築していました。そうしたなか、彼は、1957年10月7日にはボリビア国籍を取得することに成功し、この後数十年間にわたり、ボリビアの軍事政権とアメリカの事実上の庇護のもとに、バルビーはドイツ系ボリビア人の「クラウス・アルトマン」として、1964年から政権を握ったレネ・バリエントス・オルトゥーニョ将軍をはじめとする、ボリビアの軍事政権の歴代指導者の治安対策アドバイザーを務めることとなります。ボリビアの軍事政権のアドバイザーとして、バルビーは同国内で活動していた共産主義組織や反政府ゲリラ組織だけでなく、労働組合などの左翼シンパと目される組織に至るまで目を光らせ、後には1967年10月に同国の軍事政権とCIAの協力の下で行われたチェ・ゲバラの身柄確保と処刑にも関与したと報じられました。また、元ナチス党員とともにナチス再興のための組織を設立したほか、イタリアの極右政党の「イタリア社会運動(MSI)」幹部で元フリーメイソンの「ロッジP2」代表のリーチオ・ジェッリとも深い関係にあった、とされます。さらにオーストリアのシュタイア・プフなどの大手軍需企業との間の武器取引会社や海運会社を設立させて大金持ちとなっただけでなく、海運会社の役員の「クラウス・アルトマン」を名乗り、自らを戦争犯罪人ということで指名手配させていたフランスにも渡航していました。
しかし1972年に、ペルーのリマ市で発生した殺人事件の被害者と容疑者に関係のあったバルビーはリマ市警に眼をつけられます。そしてこの実業家が、実はフランスの破毀院によって死刑の判決がでている戦争犯罪人であることをつきとめられます。事件後、バルビーは公然と姿を現わし、自分の正体を認め、ボリビアのテレビに出演して、ナチス親衛隊員の過去を礼讃しました。世界のマスコミが騒然となりボリビアに殺到しました。バルビーはマスコミに『回想録』を売りつけ、戦後、西ドイツの「ゲーレン機関」に関係していたことを暴露して、世界を驚かせます。またバルビーは「戦争犯罪と考えられるいかなる行為にも関わっていない」と強く主張します。
その後もバルビーは、1980年6月に政権を奪取した民主人民連合(UDP)による左派政権に対して、同年7月17日ルイス・ガルシア・メサ・テハダ将軍が起こした軍事クーデターにも関与するなど、ボリビアの軍事政権との関係を続けました。なお、ボリビアの歴代軍事政権は、フランス政府によるバルビーの引き渡しを、バルビーが「ボリビア人」であることを根拠に公然と拒否し続けました。しかしガルシア政権は、バルビーが深く関与した左翼活動家への弾圧などにより国民からの反発を受けただけでなく、コカインの生産および輸出への深い関与が証明されたことから、後見人的立場であったアメリカの支持を失い、翌年に退陣することとなりました。
1982年、ガルシアの後を継いだボリビアの軍事政権が倒れ社会主義政権にとってかわられるとともに、バルビーをフランスに引き渡す声が高まります。翌1983年に、70歳になったバルビーは、ボリビアと同じく社会主義(フランソワ・ミッテラン)政権下にあったフランスに引き渡されました。1984年からリヨンの法廷で始まった裁判は世界中の注目を浴び、裁判においてバルビーは、「自分はフランスがアルジェリアでやったのと同じことをしたにすぎない」と主張し物議をかもした他、フランス国内の右派からは、「ヴィシー政権下で叙勲を受けるなど評価を高めたミッテラン大統領の罪状から、目をそらさせるための裁判である。」との意見もありました。しかし最終的にバルビーは終身禁固刑を宣告され、直ちにフランス国内の刑務所に収監されたのです。その後1991年9月に刑務所内で病死しました。
作中の様々なインタビューを通して、スパイ小説をも凌駕する、『真実』、が明かになります。
この作品は、「現在でも、あらゆる国家・政府は得体の知れない組織や個人と関わって、外交諜略・外交成果を上げている」という事実を、我々の前に明かにします。『外交とは、何のために存在するのか』、『外交成果とは何か』ということを、改めて我々に問う作品でした。
嘗て、『リヨンの虐殺者』という異名を与えられたバルビーが、アメリカやカトリックの総本山・バチカンからその利用価値を見出されたという「歴史事実」を私達は、一体どのように評価すればよいのでしょうか。自国の価値観に敵対するものを徹底弾圧するためには、巧みなスパイ戦術に長けたバルビーは非常に有効でありました。そして、この「利用価値あり」とされた一人のスパイを、「ラットライン」やバチカンのバックアップで生き長らえさせることを可能にしたのです。
唯、何よりも、これは事実・・・、この一点に、小生は先ず圧倒されてしまうのです。いやはやなんともです。
「スパイ」を「酒の肴」に、次回、もう一つお付き合い下さい。
では、また・・・。
(映画『敵こそ、我が友』 ~戦犯クラウス・バルビーの3つの人生~)
『クラウス・バルビー』という人物を知っていますか? 小生は、この人物の存在を、映画『敵こそ、我が友』を通して初めて知りました。彼は、1935年22歳でナチス・ドイツ親衛隊に所属してから、1987年フランスでの裁判で“終身刑(フランスは死刑がないので)”を宣告されるまでに、残虐で欺瞞に満ちた人生を送ります。本作品は、彼の人生を、「オーラル・バイオグラフィー」(いろんな人が彼について話すことで、その人物を浮かびあがらせる特殊な手法)の手法で描いた、ドキュメンタリー作品です。全編、彼に関わった人々のインタビュー(彼・本人のインタビューも含む)と、裁判映像で構成されています。
彼は、ドイツのノルトライン=ヴェストファーレン州で生まれ、1925年に、父親の転勤に伴いトリーアへと移動しました。1933年には、学生の身分ながら当時ドイツで勃興してきたナチス党のために働き、1935年には親衛隊情報部に入ります。 1939年9月に第2次世界大戦が勃発し、1942年にはドイツ占領下のオランダに赴任し、その後、フィリップ・ペタンが首班を務める親独政府であるヴィシー政権下のフランスのディジョン、リヨンに赴任します。1945年5月の終戦までの間に、ヴィシー政権下のリヨン市の治安責任者として対独抵抗運動を鎮圧する任務に就いており、8千人以上を強制移送により死に追いやり、4千人以上の殺害に関与し、1万5千人以上のレジスタンス運動の参加者に拷間を加えた責任者とされています。しかし実際には、この数字をはるかに上回る数のレジスタンスのメンバーやユダヤ人を虐殺した責任者と考えられており、また、孤児院に収容されていた44人の子供の虐殺に対する責任者とも言われたほか、レジスタンス指導者だったジャン・ムーランを逮捕し死に追いやったとのちに供述しています。フランス人は、彼に『リヨンの虐殺者』という異名を与えたそうです。
大戦後、本来ならばすぐにでもニュルンベルク裁判などの連合軍による裁判で裁かれてもおかしくなかったのですが、アメリカ軍は、フランス政府が戦犯として追求するバルビーを、当時ヨーロッパで始まりつつあった冷戦下における対ソ及びドイツ共産党員に対する情報網の設置に役立つ人物と判断し、1947年からアメリカ陸軍情報部隊(CIC)の工作員として利用します。
やがてフランスの諜報機関は、アメリカがバルビーをかくまっているという事実を嗅ぎつけ、アメリカにバルビーの引き渡しを要求しはじめました。しかしフランス政府の度重なるバルビー引き渡し要求にもかかわらず、バルビーの利用価値を高く評価していたアメリカは引き渡しを拒否し続けます。フランス政府により高まる引き渡し要求に、アメリカはバルビーを国外に逃すことを画策し、バルビーはCICが用意した「クラウス・アルトマン(Klaus Altmann)」名義のパスポートと必要書類一式を受けとり、1950年12月に家族と共に反共産主義のバチカンの庇護のもとに南アメリカに旅立ち、ファン・ペロン政権下のアルゼンチンを経て、1951年4月23日に家族と共にボリビアのラパスに到着します。フランスに彼の素性を察知されると、アメリカは『ラットライン』(ねずみの抜け道)と呼ばれた、逃走ルートを用意しました。しかも、この策動には、バチカン右派の神父たちが深く関わっていました。彼に限らず、バチカン右派の聖職者によって、ナチス残党の多くは海を渡ったようです。
1951年、彼は偽名『クラウス・アルトマン』を使い、ボリビアに潜入します。当時のボリビアは、冷戦下においてアメリカが支援する反共的な軍事政権の支配下にあり、戦前からのドイツ系移民の影響力も強かったこともあり、チリなど周辺国に住む元ナチス党員らと連絡を取り、同時に同国の軍事政権との関係を構築していました。そうしたなか、彼は、1957年10月7日にはボリビア国籍を取得することに成功し、この後数十年間にわたり、ボリビアの軍事政権とアメリカの事実上の庇護のもとに、バルビーはドイツ系ボリビア人の「クラウス・アルトマン」として、1964年から政権を握ったレネ・バリエントス・オルトゥーニョ将軍をはじめとする、ボリビアの軍事政権の歴代指導者の治安対策アドバイザーを務めることとなります。ボリビアの軍事政権のアドバイザーとして、バルビーは同国内で活動していた共産主義組織や反政府ゲリラ組織だけでなく、労働組合などの左翼シンパと目される組織に至るまで目を光らせ、後には1967年10月に同国の軍事政権とCIAの協力の下で行われたチェ・ゲバラの身柄確保と処刑にも関与したと報じられました。また、元ナチス党員とともにナチス再興のための組織を設立したほか、イタリアの極右政党の「イタリア社会運動(MSI)」幹部で元フリーメイソンの「ロッジP2」代表のリーチオ・ジェッリとも深い関係にあった、とされます。さらにオーストリアのシュタイア・プフなどの大手軍需企業との間の武器取引会社や海運会社を設立させて大金持ちとなっただけでなく、海運会社の役員の「クラウス・アルトマン」を名乗り、自らを戦争犯罪人ということで指名手配させていたフランスにも渡航していました。
しかし1972年に、ペルーのリマ市で発生した殺人事件の被害者と容疑者に関係のあったバルビーはリマ市警に眼をつけられます。そしてこの実業家が、実はフランスの破毀院によって死刑の判決がでている戦争犯罪人であることをつきとめられます。事件後、バルビーは公然と姿を現わし、自分の正体を認め、ボリビアのテレビに出演して、ナチス親衛隊員の過去を礼讃しました。世界のマスコミが騒然となりボリビアに殺到しました。バルビーはマスコミに『回想録』を売りつけ、戦後、西ドイツの「ゲーレン機関」に関係していたことを暴露して、世界を驚かせます。またバルビーは「戦争犯罪と考えられるいかなる行為にも関わっていない」と強く主張します。
その後もバルビーは、1980年6月に政権を奪取した民主人民連合(UDP)による左派政権に対して、同年7月17日ルイス・ガルシア・メサ・テハダ将軍が起こした軍事クーデターにも関与するなど、ボリビアの軍事政権との関係を続けました。なお、ボリビアの歴代軍事政権は、フランス政府によるバルビーの引き渡しを、バルビーが「ボリビア人」であることを根拠に公然と拒否し続けました。しかしガルシア政権は、バルビーが深く関与した左翼活動家への弾圧などにより国民からの反発を受けただけでなく、コカインの生産および輸出への深い関与が証明されたことから、後見人的立場であったアメリカの支持を失い、翌年に退陣することとなりました。
1982年、ガルシアの後を継いだボリビアの軍事政権が倒れ社会主義政権にとってかわられるとともに、バルビーをフランスに引き渡す声が高まります。翌1983年に、70歳になったバルビーは、ボリビアと同じく社会主義(フランソワ・ミッテラン)政権下にあったフランスに引き渡されました。1984年からリヨンの法廷で始まった裁判は世界中の注目を浴び、裁判においてバルビーは、「自分はフランスがアルジェリアでやったのと同じことをしたにすぎない」と主張し物議をかもした他、フランス国内の右派からは、「ヴィシー政権下で叙勲を受けるなど評価を高めたミッテラン大統領の罪状から、目をそらさせるための裁判である。」との意見もありました。しかし最終的にバルビーは終身禁固刑を宣告され、直ちにフランス国内の刑務所に収監されたのです。その後1991年9月に刑務所内で病死しました。
作中の様々なインタビューを通して、スパイ小説をも凌駕する、『真実』、が明かになります。
この作品は、「現在でも、あらゆる国家・政府は得体の知れない組織や個人と関わって、外交諜略・外交成果を上げている」という事実を、我々の前に明かにします。『外交とは、何のために存在するのか』、『外交成果とは何か』ということを、改めて我々に問う作品でした。
嘗て、『リヨンの虐殺者』という異名を与えられたバルビーが、アメリカやカトリックの総本山・バチカンからその利用価値を見出されたという「歴史事実」を私達は、一体どのように評価すればよいのでしょうか。自国の価値観に敵対するものを徹底弾圧するためには、巧みなスパイ戦術に長けたバルビーは非常に有効でありました。そして、この「利用価値あり」とされた一人のスパイを、「ラットライン」やバチカンのバックアップで生き長らえさせることを可能にしたのです。
唯、何よりも、これは事実・・・、この一点に、小生は先ず圧倒されてしまうのです。いやはやなんともです。
「スパイ」を「酒の肴」に、次回、もう一つお付き合い下さい。
では、また・・・。
2010年8月11日水曜日
『夢の中の夢の中の夢』で繰り広げられるアクションサスペンス、もう最高!(映画 『インセプション』に乾杯!)
「バッドマン」を変革した、あのクリスファー・ノーランが、やってくれました。誰も思いつかないであろうストーリー展開を秘めたサイコサスペンス、その名も『INCEPTION(“植えつける”と言う意味)』。
昨今は、そのほとんどが「原作アリ」というなかで、この作品『インセプション』はノーランの完全オリジナル脚本です。この物語、要するに大企業のトップ・サイトー(渡辺謙、演ずる)が、ライバル会社の社長息子を陥れてライバル会社を解体させる、というごくごく平凡なストーリーです。
では、何が「やってくれました、クリストファー・ノーラン!」なのでしょうか?それは、直ちに映画館へ行ってこの作品をご覧になれば判ります。それでは皆さん、映画館でお会いしましょう・・・、と言いたいところですが、それでは何だか判らないと思いますので、以下、熱く語りましょう。
まず、どこが「誰も思いつかない奇想天外なストーリー」なのでしょうか?それは、「サイトーがライバル会社の社長息子を陥れる手段」が斬新なのです。陥れるために用いられる手段は、なんと「夢」です。
しかも、「夢」は、陥れられるロバート(ライバル会社の社長息子)と、陥れる産業スパイ集団(ディカプリオ演ずるコブを中心とする“栄光のビッグ・ファイブ”)達とで共有されなければならない。普通、「夢」を用いて産業スパイ活動を行うというのは、「エクストラクション(作品表題のインセプションの対義語)」と解釈され、これは他人の頭の中に侵入して、カタチになる前のアイディアを盗むことなのです。しかし、今回の場合、用いられる手法は「インセプション」。それは、陥れるターゲットの意識下に「あるアイディア(この場合、会社が破滅するアイディア)」を植えつける行為なのです。
大物実業家・サイトーが雇い入れた、「産業スパイ集団」のメンバーと役割は以下の通りです。
1. 抜き取り屋のチームリーダー・コブ。
2. 複数の人間が夢の異なる状態をシェアできる薬を調合する調合師・ユスフ。
3. 夢の世界に侵入し、様々な人物に姿を変えてターゲットを翻弄する偽造師・イームス。
4. ターゲットが現実だと騙される世界を頭の中に創る設計士・アリアドネ(チーム唯一の女性)。
5. コブの心強い相棒。綿密に任務を進め、平静なポイントマン・アーサー。
具体的にストーリーを紹介しましょう。〈ネタバレ、注意!〉
主人公のドム・コブは、人の夢(潜在意識)に入り込むことでアイディアを“盗み取る”特殊な企業スパイ。 そんな彼に、強大な権力を持つ大企業のトップのサイトーが仕事を依頼してきた。依頼内容はライバル会社の解体と、会社解体を社長の息子ロバートにさせるようアイディアを“植えつける(インセプション)”ことだった。極めて困難かつ危険な内容に一度は断るものの、妻殺害の容疑をかけられ子供に会えずにいるコブは、犯罪歴の抹消を条件に仕事を引き受けた。
古くからコブと共に仕事をしてきた相棒のアーサー、夢の世界を構築する「設計士」のアリアドネ、他人になりすましターゲットの思考を誘導する「偽装師」のイームス、夢の世界を安定させる鎮静剤を作る「調合師」のユスフをメンバーに加えた6人(依頼人のサイトーも含む)で作戦を決行。首尾よくロバートの夢の中に潜入したコブ達だったが、直後に手練の兵士たちによって襲撃を受けてしまう。これはロバートが企業スパイに備えて潜在意識の防護訓練を受けており、護衛部隊を夢の中に投影させていた為であった。インセプション成功の為に更に深い階層の夢へと侵入していくコブたち。次々と襲い来るロバートの護衛部隊に加え、コブの罪悪感から生み出されたモル(=コブの妻)までもが妨害を始めた。さらに曖昧になる夢と現実の狭間、迫り来るタイムリミット、果たしてインセプションは成功するのか・・・、となるのです。
しかも、数学的にストーリーを面白くしているのは、この「夢」が「3層構造」になっているということ。
少々解説しますと、以下のようになります。しっかり話しに付いて来て下さい。
まず、「夢の世界」は、現実の世界より時間の進み方が速い、と言うことを理解して下さい。ですから、目覚める前に夢の世界から出るには、自分を殺すか、外部から衝撃を与えてもらう(=「キック」と言います。)しか方法は無いのです。ですから、「夢の階層」を次の階層へと進む時は、チームの誰かが、「(現在入り込んでいる)夢の階層」に残留しなければならないのです。
また、夢の世界を創る際、記憶をもとに設計すると夢と現実の区別がつかなくなる危険があります。
(現実) ロサンゼルス行き飛行機の中(飛行機はサイトーが全部買い占める。)
1. (夢の第一階層での作戦) ロサンゼルスを舞台に、ロバートが父との関係を見つめなおすように誘惑し、遺言の存在を意識させる。 「残留」は調合師のユフス。
2. (夢の第2階層での作戦) とある高級ホテルを舞台に、ロバートに「自分で何かを作りたい」という意識を刷り込み、「遺言書」を狙う法律顧問のブラウニングにエクストラクト(=夢を見ている間に、その潜在意識に入り込みアイディアを抜取ること)を仕掛けるとロバートに思い込ませる。「残留」は、アーサー。
3. (夢の第3階層での作戦) 雪山にある病院を舞台に、ロバートを病床の父親と引き合わせ、「父のあとを継ぐのでなく、自分の道を進む」というアイディアを植えつける。「残留」は、イームス。
どうですか?付いて来られましたか?
夢と現実という二元世界をあれこれ楽しむ流儀は昔から人類に染みついています。仮想空間を作らないと誰も現実に耐えられないからでしょうか。小説、演劇、アートなどはそもそも必要に応じて作り出された仮想空間そのもので、人はそこに入り込み、別のリアルを模索するのであります。
ドラッグによる脳内神経の化学反応で現実を攪拌する方法は、様々な映画作品に取り入れられています。また、{夢の中の夢}まではシェークスピアも用いましたが、この「インセプション」と言う作品のなかで、ロバートに{植え付け}任務を遂行する「仮想空間」は、『夢の中の夢の中の夢』という深層なのです。非常に、緻密なストーリー構成で、しかも、仮想空間・夢の3層構造は同時進行していきますので、スリリングでもあります。本当に、このようなアイディアに完敗であり、乾杯なのです。
どうぞ、是非、この数学的な緻密でスリリングなストーリー構成に、あなたも劇場で酔いしれてみて下さい。
本日は、見事な「ストーリー構成」の紹介が「酒の肴」となってしまいました。でも、このような「肴」も格別です。
では、また・・・。
昨今は、そのほとんどが「原作アリ」というなかで、この作品『インセプション』はノーランの完全オリジナル脚本です。この物語、要するに大企業のトップ・サイトー(渡辺謙、演ずる)が、ライバル会社の社長息子を陥れてライバル会社を解体させる、というごくごく平凡なストーリーです。
では、何が「やってくれました、クリストファー・ノーラン!」なのでしょうか?それは、直ちに映画館へ行ってこの作品をご覧になれば判ります。それでは皆さん、映画館でお会いしましょう・・・、と言いたいところですが、それでは何だか判らないと思いますので、以下、熱く語りましょう。
まず、どこが「誰も思いつかない奇想天外なストーリー」なのでしょうか?それは、「サイトーがライバル会社の社長息子を陥れる手段」が斬新なのです。陥れるために用いられる手段は、なんと「夢」です。
しかも、「夢」は、陥れられるロバート(ライバル会社の社長息子)と、陥れる産業スパイ集団(ディカプリオ演ずるコブを中心とする“栄光のビッグ・ファイブ”)達とで共有されなければならない。普通、「夢」を用いて産業スパイ活動を行うというのは、「エクストラクション(作品表題のインセプションの対義語)」と解釈され、これは他人の頭の中に侵入して、カタチになる前のアイディアを盗むことなのです。しかし、今回の場合、用いられる手法は「インセプション」。それは、陥れるターゲットの意識下に「あるアイディア(この場合、会社が破滅するアイディア)」を植えつける行為なのです。
大物実業家・サイトーが雇い入れた、「産業スパイ集団」のメンバーと役割は以下の通りです。
1. 抜き取り屋のチームリーダー・コブ。
2. 複数の人間が夢の異なる状態をシェアできる薬を調合する調合師・ユスフ。
3. 夢の世界に侵入し、様々な人物に姿を変えてターゲットを翻弄する偽造師・イームス。
4. ターゲットが現実だと騙される世界を頭の中に創る設計士・アリアドネ(チーム唯一の女性)。
5. コブの心強い相棒。綿密に任務を進め、平静なポイントマン・アーサー。
具体的にストーリーを紹介しましょう。〈ネタバレ、注意!〉
主人公のドム・コブは、人の夢(潜在意識)に入り込むことでアイディアを“盗み取る”特殊な企業スパイ。 そんな彼に、強大な権力を持つ大企業のトップのサイトーが仕事を依頼してきた。依頼内容はライバル会社の解体と、会社解体を社長の息子ロバートにさせるようアイディアを“植えつける(インセプション)”ことだった。極めて困難かつ危険な内容に一度は断るものの、妻殺害の容疑をかけられ子供に会えずにいるコブは、犯罪歴の抹消を条件に仕事を引き受けた。
古くからコブと共に仕事をしてきた相棒のアーサー、夢の世界を構築する「設計士」のアリアドネ、他人になりすましターゲットの思考を誘導する「偽装師」のイームス、夢の世界を安定させる鎮静剤を作る「調合師」のユスフをメンバーに加えた6人(依頼人のサイトーも含む)で作戦を決行。首尾よくロバートの夢の中に潜入したコブ達だったが、直後に手練の兵士たちによって襲撃を受けてしまう。これはロバートが企業スパイに備えて潜在意識の防護訓練を受けており、護衛部隊を夢の中に投影させていた為であった。インセプション成功の為に更に深い階層の夢へと侵入していくコブたち。次々と襲い来るロバートの護衛部隊に加え、コブの罪悪感から生み出されたモル(=コブの妻)までもが妨害を始めた。さらに曖昧になる夢と現実の狭間、迫り来るタイムリミット、果たしてインセプションは成功するのか・・・、となるのです。
しかも、数学的にストーリーを面白くしているのは、この「夢」が「3層構造」になっているということ。
少々解説しますと、以下のようになります。しっかり話しに付いて来て下さい。
まず、「夢の世界」は、現実の世界より時間の進み方が速い、と言うことを理解して下さい。ですから、目覚める前に夢の世界から出るには、自分を殺すか、外部から衝撃を与えてもらう(=「キック」と言います。)しか方法は無いのです。ですから、「夢の階層」を次の階層へと進む時は、チームの誰かが、「(現在入り込んでいる)夢の階層」に残留しなければならないのです。
また、夢の世界を創る際、記憶をもとに設計すると夢と現実の区別がつかなくなる危険があります。
(現実) ロサンゼルス行き飛行機の中(飛行機はサイトーが全部買い占める。)
1. (夢の第一階層での作戦) ロサンゼルスを舞台に、ロバートが父との関係を見つめなおすように誘惑し、遺言の存在を意識させる。 「残留」は調合師のユフス。
2. (夢の第2階層での作戦) とある高級ホテルを舞台に、ロバートに「自分で何かを作りたい」という意識を刷り込み、「遺言書」を狙う法律顧問のブラウニングにエクストラクト(=夢を見ている間に、その潜在意識に入り込みアイディアを抜取ること)を仕掛けるとロバートに思い込ませる。「残留」は、アーサー。
3. (夢の第3階層での作戦) 雪山にある病院を舞台に、ロバートを病床の父親と引き合わせ、「父のあとを継ぐのでなく、自分の道を進む」というアイディアを植えつける。「残留」は、イームス。
どうですか?付いて来られましたか?
夢と現実という二元世界をあれこれ楽しむ流儀は昔から人類に染みついています。仮想空間を作らないと誰も現実に耐えられないからでしょうか。小説、演劇、アートなどはそもそも必要に応じて作り出された仮想空間そのもので、人はそこに入り込み、別のリアルを模索するのであります。
ドラッグによる脳内神経の化学反応で現実を攪拌する方法は、様々な映画作品に取り入れられています。また、{夢の中の夢}まではシェークスピアも用いましたが、この「インセプション」と言う作品のなかで、ロバートに{植え付け}任務を遂行する「仮想空間」は、『夢の中の夢の中の夢』という深層なのです。非常に、緻密なストーリー構成で、しかも、仮想空間・夢の3層構造は同時進行していきますので、スリリングでもあります。本当に、このようなアイディアに完敗であり、乾杯なのです。
どうぞ、是非、この数学的な緻密でスリリングなストーリー構成に、あなたも劇場で酔いしれてみて下さい。
本日は、見事な「ストーリー構成」の紹介が「酒の肴」となってしまいました。でも、このような「肴」も格別です。
では、また・・・。
2010年8月2日月曜日
悩むこと、それは素晴らしいこと。映画『パリ20区、僕たちのクラス』を見て感じたこと。
映画:『パリ20区、僕たちのクラス』は、移民の子弟の多い「パリ20区」(⇒ 小生、この「パリ20区」、全く存じ上げませんでした。)地区のある中学校で、理想主義に燃えた教師の奮闘と生徒とのやりとりを、ドキュメンタリーかと見まがうタッチで描いた作品です。
(1)映画について
第61回カンヌ国際映画祭で、審査委員長ショーン・ペンが絶賛しパルムドールに選んだ奇跡のような傑作、といわれています。21年ぶりに、フランス映画にパルムドールの栄誉をもたらしました。新聞や雑誌の映画評が、あまりにも高評価なので、小生も、久しぶりに“岩波ホール”へ足を向けました。
この映画が、多くの方々から評価を受けるのは主に、以下の3点です。
1. ドキュメンタリーとしか思えないほどの自然な演技に驚嘆し、先の読めないストーリー展開に胸を躍らせること。
2. フランソワ役の原作者フランソワ・ベゴドーをはじめ、映画に登場する教師も生徒もすべて素人なのに、ローラン・カンテ監督による丹念なワークショップの賜物か、別人になり切る見事な演技を見せてくれること。
3. 安直な和解とは無縁なリアリティに満ちた展開が、観る者を唸らせること。つまり、奮闘する教師・フランソワの思い描くように事態は展開しないのです。しかし、だからこそ、オーディエンスが、いつの間にか、作品に登場する生徒の誰かに、自らの中学生時代に自分が出会ってきた誰かを重ね合わせ、感情移入せずにはいられなくなるのです。
原題は『Entre les Murs』で、直訳すれば「壁の間で」となりますが、なぜか日本人のブログやWeb上での紹介では「壁の中で」と訳しているケースが多いそうです。原題は、教室内コミュニケーションにおける教師と生徒との間の障壁、そして生徒の中での民族間の障壁を象徴しているものだと思います。原作者本人が脚色に携わると同時に自ら教師役として出演しています。
(2)ストーリー
舞台は、移民が多く暮らすパリ20区の公立中学校・新学期の教室。この中学では生徒の大半が移民の子弟で、母語も出身国もバラバラ。そんな中で、正しい国語を身につけさせることこそ生徒たちの将来の幸福につながるという信念を持つ主人公のフランス語教師・フランソワが、様々な出身国を持つ24人の生徒たちが混じり合う教室のなかで、思いがけない反発や質問に翻弄されてしまいます。現実は情熱だけで解決できるような簡単なものではないのです。
例えば、去年は素直だったクンバは反抗的な態度で教科書の朗読さえ拒否する始末。また、自己紹介文を書かせる課題が大きな波紋を巻き起します。教室の中は真剣勝負の場です。教師も生徒も真っ向からぶつかり合います。ゆえに言葉というものの重要性が浮き彫りになります。誤解も批判も怒りも失望も、そして希望も言葉あってこそのもの。子どもたちのフランス語の力は、確かに日常会話ならほぼ不自由なく使えます。しかし動詞の活用は不確かだし、文語で主に使われる接続法の活用や、抽象的な単語は十分な理解が出来ない状況…。
さらに、フランス人の親は、この学校はレベルが低いから自分の息子は転校させたい、と言い出すような学校であります。始業のベルが鳴ってもお喋りはやまず、授業に身が入らない子どもも多いのです。教師の中でも、レベルの低い馬鹿どもを相手に小学校で教えるようなことから教えなきゃならないのは耐えられないと愚痴をこぼすような者がいる状況です。ちょっとすればすぐ注意力が逸れたり、教師の指示に従おうとしない生徒たちに手を焼く毎日です。生徒の反抗的な態度に、フランソワ自身、頭に来て椅子を蹴飛ばして憂さを晴らすことも・・・。
しかし、生徒たちが教師を恐れなくなり指示を聞かないからと、ポイント減点制を導入し、一定のポイントに達した生徒は教育委員会に退学を諮ることにしようという一部の教師の提案には、フランソワは断固反対する。また、親がフランス語を話せず、本人も自分の学業に自信を持てない生徒の長所を発見して、彼の才能を発揮できる機会を作り、学業を続けさせる意欲をかき立てることにも成功します。
(そのようななかで、決定的な事件が起こります。)
生徒の成績評価会議に、生徒代表としてオブザーバー参加していた二人の女子生徒が、無責任にもそこでの会議内容をクラス内で話し、成績の悪い生徒を馬鹿呼ばわりしたことに対し、フランソワは怒って、ついその生徒をpetasse(ずべ公、売春婦)と呼びつけてしまうことで、フランソワのクラスにおける信用は一夜にして瓦解してしまいます。彼の努力は一部功を奏しながらも、結局はほんの一瞬の失敗により全ての努力は水の泡となり、生徒たちとフランソワの間の信頼関係は崩壊するのです。さらに手を掛けた生徒から退学者も出てしまう。さて、フランソワは、生徒達との信頼関係を取り戻せるのか・・・。
(3)監督について
監督のローラン・カンテは1961年フランス、ドゥー=セーヴル県、メル生まれです。1999年『人材 (Ressources humaines)』で労使対立に起因する労働者の苦難を描いて国際的に注目されます。さらに2001年リストラされたものの家族に悟られないよう仕事に行くふりをする男を描いた『時間労働 (L'imploi du temps)』、2005年、1970年代末を背景に、ハイチへ黒人男を漁りに行く3人のフランス人白人中年女性を描いた『南へ (Vers Le Sud)』を撮っています。
今回のこの作品で、カンテ監督が子供たちから自然な演技を引き出した秘密は、撮影前のワークショップにある、と言われています。中学校で希望者を募って週1回、約7ヶ月間、彼ら一人一人の個性を把握し、能力を探り続けた、そうです。そして、最後まで通い続けた生徒たちの中から、この24人を選んだそうです。子供たちの設定は、すべてフィクションです。彼ら自身の性格を少し取り入れたキャラクターもあるが、ほとんどが自分とは全く違う生徒を演じています。監督を始めスタッフ、キャストの大人たちは、彼らの潜在能力に感動した、とコメントしています。
(4)小生の感慨
教師たちは、決して聖職者ではなく、悩み苦しむ人間らしい労働者として描かれます。
小生、様々な出会いを求めて日々活動しておりますが、今、小生が語り合いたい方、それは「希望を求めて、悩み苦しみ、日々試行錯誤しておられる方」です。主人公が、真面目であるが故に、生徒の不真面目さが許せず生徒とぶつかり合う姿には、「俺、あんたの気持、よく判るよ!」と声を掛けたくなります。
試行錯誤を行う人間は「不器用」という言葉で、片付けられてしまう昨今ですが、試行錯誤を避けていては「希望」を勝ち得ることは不可能だと思います。私達は、無人島で暮らすロビンソー・クルーソーではないのですから・・・。
自分のセンスを全く理解しようとしない方とのコミュニケーションは非常に不愉快なものです。しかし、この不愉快さを、いかに克服していくのか、に悩むのです。この映画の主人公も、反抗的で、自己中心的で、ヒトの気持(=紳士に生徒を心配する気持)を理解しようとしない生徒と対峙することは非常に苦痛であった筈です。しかし、彼は試行錯誤を続けた。小生、ここに彼と共感するのです。全てが生々しく、あたかもドキュメンタリーの様にこの先どう転ぶか分からない緊迫感に溢れている「リアリティ」を突きつける作品です。
それにしても、成績判定会議に生徒代表がオブザーバーとして立ち合うなど、彼我の学校文化の差には驚かされます。また生徒たちも、騒いだりするとは言え、基本的には先生に注目して欲しいし、先生とコミュニケーションを取ろうとする姿勢が、一般的な日本人あるいは日本の学校システムとかなり違うように思われます。
まぁ~、ここで日仏間の学校教育のありかたを論ずるつもりはありません。小生、スクリーンのなかで、本気で悩んでいる教師・フランソワと出会い、「悩むこと、それは素晴らしいこと」と言う思いを強くしました。そうした気持を、今回はお伝えしたかったのです。
さぁ~、本日の「酒の肴」、御堪能頂けましたでしょうか。それでは、また・・・。
(1)映画について
第61回カンヌ国際映画祭で、審査委員長ショーン・ペンが絶賛しパルムドールに選んだ奇跡のような傑作、といわれています。21年ぶりに、フランス映画にパルムドールの栄誉をもたらしました。新聞や雑誌の映画評が、あまりにも高評価なので、小生も、久しぶりに“岩波ホール”へ足を向けました。
この映画が、多くの方々から評価を受けるのは主に、以下の3点です。
1. ドキュメンタリーとしか思えないほどの自然な演技に驚嘆し、先の読めないストーリー展開に胸を躍らせること。
2. フランソワ役の原作者フランソワ・ベゴドーをはじめ、映画に登場する教師も生徒もすべて素人なのに、ローラン・カンテ監督による丹念なワークショップの賜物か、別人になり切る見事な演技を見せてくれること。
3. 安直な和解とは無縁なリアリティに満ちた展開が、観る者を唸らせること。つまり、奮闘する教師・フランソワの思い描くように事態は展開しないのです。しかし、だからこそ、オーディエンスが、いつの間にか、作品に登場する生徒の誰かに、自らの中学生時代に自分が出会ってきた誰かを重ね合わせ、感情移入せずにはいられなくなるのです。
原題は『Entre les Murs』で、直訳すれば「壁の間で」となりますが、なぜか日本人のブログやWeb上での紹介では「壁の中で」と訳しているケースが多いそうです。原題は、教室内コミュニケーションにおける教師と生徒との間の障壁、そして生徒の中での民族間の障壁を象徴しているものだと思います。原作者本人が脚色に携わると同時に自ら教師役として出演しています。
(2)ストーリー
舞台は、移民が多く暮らすパリ20区の公立中学校・新学期の教室。この中学では生徒の大半が移民の子弟で、母語も出身国もバラバラ。そんな中で、正しい国語を身につけさせることこそ生徒たちの将来の幸福につながるという信念を持つ主人公のフランス語教師・フランソワが、様々な出身国を持つ24人の生徒たちが混じり合う教室のなかで、思いがけない反発や質問に翻弄されてしまいます。現実は情熱だけで解決できるような簡単なものではないのです。
例えば、去年は素直だったクンバは反抗的な態度で教科書の朗読さえ拒否する始末。また、自己紹介文を書かせる課題が大きな波紋を巻き起します。教室の中は真剣勝負の場です。教師も生徒も真っ向からぶつかり合います。ゆえに言葉というものの重要性が浮き彫りになります。誤解も批判も怒りも失望も、そして希望も言葉あってこそのもの。子どもたちのフランス語の力は、確かに日常会話ならほぼ不自由なく使えます。しかし動詞の活用は不確かだし、文語で主に使われる接続法の活用や、抽象的な単語は十分な理解が出来ない状況…。
さらに、フランス人の親は、この学校はレベルが低いから自分の息子は転校させたい、と言い出すような学校であります。始業のベルが鳴ってもお喋りはやまず、授業に身が入らない子どもも多いのです。教師の中でも、レベルの低い馬鹿どもを相手に小学校で教えるようなことから教えなきゃならないのは耐えられないと愚痴をこぼすような者がいる状況です。ちょっとすればすぐ注意力が逸れたり、教師の指示に従おうとしない生徒たちに手を焼く毎日です。生徒の反抗的な態度に、フランソワ自身、頭に来て椅子を蹴飛ばして憂さを晴らすことも・・・。
しかし、生徒たちが教師を恐れなくなり指示を聞かないからと、ポイント減点制を導入し、一定のポイントに達した生徒は教育委員会に退学を諮ることにしようという一部の教師の提案には、フランソワは断固反対する。また、親がフランス語を話せず、本人も自分の学業に自信を持てない生徒の長所を発見して、彼の才能を発揮できる機会を作り、学業を続けさせる意欲をかき立てることにも成功します。
(そのようななかで、決定的な事件が起こります。)
生徒の成績評価会議に、生徒代表としてオブザーバー参加していた二人の女子生徒が、無責任にもそこでの会議内容をクラス内で話し、成績の悪い生徒を馬鹿呼ばわりしたことに対し、フランソワは怒って、ついその生徒をpetasse(ずべ公、売春婦)と呼びつけてしまうことで、フランソワのクラスにおける信用は一夜にして瓦解してしまいます。彼の努力は一部功を奏しながらも、結局はほんの一瞬の失敗により全ての努力は水の泡となり、生徒たちとフランソワの間の信頼関係は崩壊するのです。さらに手を掛けた生徒から退学者も出てしまう。さて、フランソワは、生徒達との信頼関係を取り戻せるのか・・・。
(3)監督について
監督のローラン・カンテは1961年フランス、ドゥー=セーヴル県、メル生まれです。1999年『人材 (Ressources humaines)』で労使対立に起因する労働者の苦難を描いて国際的に注目されます。さらに2001年リストラされたものの家族に悟られないよう仕事に行くふりをする男を描いた『時間労働 (L'imploi du temps)』、2005年、1970年代末を背景に、ハイチへ黒人男を漁りに行く3人のフランス人白人中年女性を描いた『南へ (Vers Le Sud)』を撮っています。
今回のこの作品で、カンテ監督が子供たちから自然な演技を引き出した秘密は、撮影前のワークショップにある、と言われています。中学校で希望者を募って週1回、約7ヶ月間、彼ら一人一人の個性を把握し、能力を探り続けた、そうです。そして、最後まで通い続けた生徒たちの中から、この24人を選んだそうです。子供たちの設定は、すべてフィクションです。彼ら自身の性格を少し取り入れたキャラクターもあるが、ほとんどが自分とは全く違う生徒を演じています。監督を始めスタッフ、キャストの大人たちは、彼らの潜在能力に感動した、とコメントしています。
(4)小生の感慨
教師たちは、決して聖職者ではなく、悩み苦しむ人間らしい労働者として描かれます。
小生、様々な出会いを求めて日々活動しておりますが、今、小生が語り合いたい方、それは「希望を求めて、悩み苦しみ、日々試行錯誤しておられる方」です。主人公が、真面目であるが故に、生徒の不真面目さが許せず生徒とぶつかり合う姿には、「俺、あんたの気持、よく判るよ!」と声を掛けたくなります。
試行錯誤を行う人間は「不器用」という言葉で、片付けられてしまう昨今ですが、試行錯誤を避けていては「希望」を勝ち得ることは不可能だと思います。私達は、無人島で暮らすロビンソー・クルーソーではないのですから・・・。
自分のセンスを全く理解しようとしない方とのコミュニケーションは非常に不愉快なものです。しかし、この不愉快さを、いかに克服していくのか、に悩むのです。この映画の主人公も、反抗的で、自己中心的で、ヒトの気持(=紳士に生徒を心配する気持)を理解しようとしない生徒と対峙することは非常に苦痛であった筈です。しかし、彼は試行錯誤を続けた。小生、ここに彼と共感するのです。全てが生々しく、あたかもドキュメンタリーの様にこの先どう転ぶか分からない緊迫感に溢れている「リアリティ」を突きつける作品です。
それにしても、成績判定会議に生徒代表がオブザーバーとして立ち合うなど、彼我の学校文化の差には驚かされます。また生徒たちも、騒いだりするとは言え、基本的には先生に注目して欲しいし、先生とコミュニケーションを取ろうとする姿勢が、一般的な日本人あるいは日本の学校システムとかなり違うように思われます。
まぁ~、ここで日仏間の学校教育のありかたを論ずるつもりはありません。小生、スクリーンのなかで、本気で悩んでいる教師・フランソワと出会い、「悩むこと、それは素晴らしいこと」と言う思いを強くしました。そうした気持を、今回はお伝えしたかったのです。
さぁ~、本日の「酒の肴」、御堪能頂けましたでしょうか。それでは、また・・・。
登録:
コメント (Atom)